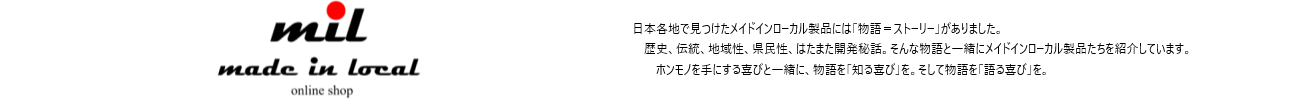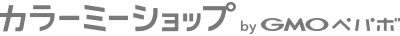Story
■カワイ 若狭塗箸 にっぽん伝統色箸 のストーリー
『お箸と漢字の国の人だからこそ』

「常盤緑」という色をご存じだろうか。
そう「みどりいろ」である。
ただ、この「常盤緑」はただのみどりではない。
「常盤」とは永久に変わらない、ということを指す。
この常盤緑は、日本の山にある冬でも緑の葉を保つ、
「常緑樹の緑」の葉の色である。
「山吹色」という色は当然知らぬ人はまずいないだろう。
いわゆる「オレンジ色」とお思いの人もいるかもしれない。
ただ、この「山吹色」は果物のオレンジの色ではない。
「山吹」とは日本の山にちらほらと見られる
「ヤマブキの花」の色である。
これらの色は「日本の伝統色」である。
日本人が「ブルー」や「ピンク」という言葉を知る前に、
自然に息づくものを色の例えにしたのである。
一口に「青」と言っても伝統色の青系に属する色の名前は
感動すら覚える感受性あふれる名付けである。
紺、藍、青、のあたりは基本であるが、
紫がかった「茄子紺」、くすみを帯びた「鉄紺」、
寒色系にも関わらず、華やかさすら感じさせる「紺碧」。
その中でも「藍白」は面白い。
藍染の回数が非常に少ない状態の藍色のことである。
実は「甕覗(かめのぞき)」と言われることが多いようで、
藍染の甕に布をちょっと浸しただけ、つまり「覗いた」だけ、
といういわれのようである。(諸説あり)
そして、別名「白殺し」!
最初は白いさらしの布が藍で染められることで青くなっていくわけだが、
この時点で「白くなくなる」、つまり「白殺し」なのである。
身近な自然に色の名を求めたかと思えば、
洒落を効かせた名付けをする。
わずかな違いも見逃さず、
その色に近い言葉を探し当てはめたかと思えば、
遠い色を当てはめて「殺し」てみせる。
豊かな自然と、さらに豊かな表情を見せる日本の四季。
そして古代中国から伝わって、独自に進化した漢字と、
さらにさらに独自で発達した日本語そのものという言語文化が重なり合ってできた、
奇跡の名前をもつ色、それが「日本の伝統色」なのだ。

カワイ(株)は塗箸生産日本一の町、福井県小浜にある。
戦時中の開業以来、いわゆる塗箸を作ってきた。
そして今も小浜の誇る地場産業の雄として塗箸を製造している。
この「にっぽん伝統色箸」の開発を主導した、営業企画部長の幸池氏は、
日本の伝統色をカワイの箸で表現できないか、と構想していたという。
「お箸を作る者」として、
食卓に彩りをもたらす箸によって、
より食卓に喜びや楽しさを届ける方法はないだろうか、と常々考えていた。
たしかに箸は古代中国から伝わったというが、
日本で独自の進化を経て、塗箸のような現在の姿に至る。
日本の伝統色もしかり。
日本独自の文化が交わることで、様々な色の表現を得た。
「箸と伝統色、これが合致しないわけがない!」
幸池部長は確信をもって、開発に着手したのである。
「にっぽん伝統色箸」は、
日本の自然と文化の結晶である「伝統色」と
日本の独自の文化の象徴である「箸」とが手に手をとった、
まさに「奇跡の箸」なのである。
我々は「お箸の国」の人である。
そして「漢字の国」の人である。
だからこそ、この「奇跡の箸」を手にしてほしいのである。

■色を知り、日本語の奥深さを知る
「素色(【しろいろ】)」

音どおりの「白」ではない。
「白」は漂白されたものの色で、
「素」はその漂白される前の絹の色だという。
この「素」を【しろ】とは読めなさそうだが、
実は普通に使っている。そう、「素人」は【しろうと】ではないか。
つまり、何も手が加わっていない、ということなのだろう。
まさに無垢の美しさ。
何も引かれず、何も足されない、自然そのままの色だからこそ、
手に取って落ち着くし、優しい気持ちになれるのかもしれない。
「若葉色【わかばいろ】」

「黄緑色だ」と言ってしまうと野暮だろう。
黄緑色より黄色味は低く、緑も明るい。
まさしく、若葉のみずみずしいエネルギーを感じさせる色である。
「若」が付く色は、
「若草色」「若菜色」「若竹色」など多く存在し、
共通して明るい色である。
「若さ」は生命力の発露であり、
色として表現されると、それは明るさ、爽やかさが現れるのだ。
「常盤緑【ときわみどり】」

常緑樹の葉の色、である。
秋に紅葉し、冬に葉を落とす落葉樹も風情があるのだが、
この常緑樹は濃くつややかな緑を常にたたえるエネルギーに満ちた色である。
若葉色同様、常盤緑も葉の色であるが、
緑の木の葉は「生命力の発露」である。
山に登り、緑に囲まれて、おいしい空気を吸うだけでなく、
目にも緑を与えてやってほしい。
美しい緑は生命力を目からも吸収させてくれるのだ。
「桜色【さくらいろ】」

桜の花びらの色である。
「ピンク色」というにはあまりに儚い色ではないか。
薄いピンク色であることには違いないが、
むしろ白に近いといっていいだろう。
乙女のはにかむ頬の色とでも言えるだろうか。
桜色は桜の花びらで染められたものではなく、
ベニバナの色である。大量に使用することで紅色を得られるが、
ベニバナは高価であったため、少量のベニバナで染めることで桜色を得る。
この儚くも可憐な色が安価でできるゆえに、人気が高かったのは言うまでもない。
「柿色【かきいろ】」

実際に熟れた柿ほどの濃さはないが、若い柿の力をたたえた明るさを持つ。
柿は秋の味覚の代表格だが、
目にもおいしいことは請け合いである。
オレンジ色ほど鮮やかではないが、
明るいながらも味のあるだいだい色、といえばよいだろうか。
有名な話ではあるが、
いわゆるオレンジ系の色は「食欲をそそる色」である。
秋の味覚、柿の色が施されたお箸で食べるごはんはおいしいだろうなぁ。
そう、でも、食べ過ぎには要注意。
「桃花色【ももいろ】」

桃も桜も種類にもいろいろあるので一概に言えないが、
桃の花は桜の花の色よりやや濃く、華やかに見えるというのが
一般的なようである。
桜の花びらは先が分かれているが、桃の花は先が分かれずにとがっている、
というのが見分ける特徴である。
桃は桜より花一つでは華やかであるが、
花の数が桜ほどではないため、全体としての華やかさは桜の後塵を拝する。
桃は1本の木が多くの実をみのらせることから、
生命力の代名詞ともいわれ、
華やかで、活発な女性をイメージさせる。
桃花色もやはり、桜色の儚さに比して、活発でいきいきとした力を感じさせる色である。
「藍白【あいじろ】」

ストーリーの通り。
別名「白殺し」。
殺伐とした名だがこれは言葉遊びと言っていい。
食卓に遊び心が持ち込まれると、
当然、食卓はもっと楽しくなる。
「藤色【ふじいろ】」

いわずと知れた「藤の花」の色である。
薄い紫色というと、どうも風情に欠ける。
古来日本では紫色は高貴な色であり、
聖徳太子の冠位十二階の最上級の冠は紫色だった、と聞いたことがある人がいるのでは。
(諸説あり。紫色だった、というのが有力、というレベルのようです)
古くから多くの人に好まれ、衣類にも多く使われる人気色だったようだ。
濃くはっきりした紫色ではなく、
優しい色彩を持つ藤色は女性にも好まれ続けている。
その他多くの色の名に花の色は用いられている。
花は古くから人の生活に密着し、心安らぐものであった証明であろう。
「紺碧【こんぺき】」

「紺」は藍染のもっとも濃い色である。
紫がかった濃い青、といえばよいだろうか。
では、
「碧」は?
「あお」とも「みどり」とも読むのだ。
「碧玉」は鉱物であり、石英の集合物を指す。
「碧玉」は緑碧玉もあれば、赤碧玉もあるようなので、
いちがいに「碧」の色、とも言えないようだ。
いわば、「青のような、緑のような色」である。
では、これが交わった「紺碧」とは?
紺は深く、濃いイメージだろう。
碧は明るく、軽いイメージではないだろうか。
深く濃く、明るく、軽い、青、である。
こんな色はどこにあるのだろう。
そう、紺碧の空、紺碧の海、というように使われるではないか。
つまり、大自然は深く、濃く、明るく、軽やかなのだ。
相反するように見えて、すべてを含んでいる。
自然って偉大だ。
「深緋(【こきひ】/【こきあか】とも)」

深緋、は赤色に属する色であるが、茜(アカネ)と紫根(シコン)で染めたものの色である。
茜は音のとおり赤い根であり、紫根はムラサキという草の根である。
ここから、やや紫を帯びた茜色、といえるだろう。
この「深」を「こき」と読むのはまさに「濃い」という意味からであろう。
緋色は鮮やかな赤、と言えるが、それが濃く深い色、つまり「深緋」である。
同様に、非常に濃い青に「深縹」もあり、これも「こきはなだ」と読む。
「深」を「ふか」と読まずに「こき」と読む、
日本語はやっぱり、奥が「深い」。
「古代朱【こだいしゅ】」

「朱色」は黄色味を帯びた赤を指す。
元々は「辰砂(しんしゃ)」という硫化水銀の天然鉱石の色、である。
この辰砂、「賢者の石」という通り名があり、
錬金術や錬丹術といった古代の科学における重要な鉱物だったようだ。
「古代朱」は朱色の類でも、
ツヤをおさえた、渋みのある色である。
日本でも古くからある赤い漆の色、である。
日本人の特有の奥ゆかしさと、落ち着きが表現されつつも、
深い色合いは華やかさすら感じさせる。
古くから親しまれ、ずっと受け継がれてきた色である。
つまり、それだけ美しい色、なのだ。
「漆黒【しっこく】」

文字通り、黒漆(くろうるし)が塗られたものの色である。
深く濃く、なにより「艶」がある黒のことだ。
「艶」は単なる「ぴかぴかしたツヤ」だけを意味しないところ面白い。
いわば「濡れ色」であり、みずみずしさすらたたえる光沢をもつ黒なのだ。
「艶やか」は「つややか」とも「あでやか」とも読む。
なまめかしさや華やかさや色気を持った美しさのことを指すが、
とにかく、美しいものに使われる「ツヤ」である。
黒はすべての可視光線を吸収し、反射しないため黒く見える。
そう、「黒」は美しい。
深い「黒」に視線まで吸い込まれてしまうほどに。
「杜若色【かきつばたいろ】」

明るい赤みのある紫である。
「いずれアヤメかカキツバタ」という言葉を聞いたことがある人もいるだろう。
ともに美しくて甲乙つけがたい、という意味でつかわれるが、
実際の花はともに美しいのはそのとおりだが、とにかくよく似ている。
詳しい人でないと、すぐには見分けがつかないだろう。
そして、ショウブもアヤメと同じ「菖蒲」の文字を使うが、
ショウブは美しい花をつけない。
さらにややこしいのは、「花菖蒲(ハナショウブ)」の存在である。
ハナショウブもアヤメやカキツバタと同じ美しい花をつけるが・・・
このネーミング、漢字の当て方、日本語は難しい・・・
これらの詳しい違いはご自身で調べてみては?
この違いを語れれば、かなりな自慢になること間違いなし。
「山吹色【やまぶきいろ】」

赤みを帯びた鮮やかな黄色、といえばよいだろうか。
日本の野山に見られるヤマブキの花の色である。
黄金色に近いが、光沢のあるいわゆるゴールド、ではなく、
落ち着いた黄金色、といえばよいだろうか。
時代劇で、小判のことを「ヤマブキ」と言っているのを聞いたことはないだろうか。
小判の黄金色がまさにヤマブキの色を想起させるため、使われるようになったようだ。
当然、気の持ちようだが、金運を招きいれたいなら、
山吹色のものはうってつけ、かもしれない。
「茄子紺【なすこん】」

いわずと知れた「ナスの色」、と言いたいところだが、
ナスの実のような紫を帯びた紺色、である。
箱根駅伝ファンなら、順天堂大のユニフォーム、とまず思うのでは。
ちなみに、英語では「dusky purple(もしくはblue)」のようだ。
「dusky」は浅黒い、黒ずんだ、という意味のようなので、
あまりいいイメージを持てない。
この茄子紺は、夏のナスのみずみずしさを思い浮かべてしまうような
黒ずんだ、や浅黒い、とは程遠い「美しい」色である。
これも身近な自然に色の名を求める、日本人らしさからくる名付け、と言えるのではないだろうか。
日本語を語るのは楽しい。
本当に面「白い」話や楽しい発見が「いろいろ」あるから。